そもそも源三位入道という人は、摂津守頼光から五代、三河守頼綱の孫、兵庫頭仲政の子である。保元の乱の時は後白河天皇方につき、真っ先に敵の中に攻めこんだけれど、これといった恩賞は与えられなかった。また平治の乱でも、親兄弟を捨てて平氏に味方したが、恩賞はわずかだった。大内裏を長年警固したけれど、昇殿を許されなかった。年を重ね老齢になってから、述懐の和歌一首を詠んで、昇殿を許されたのだった。
人知れず大内山のやまもりは 木がくれてのみ月をみるかな=人に知られることもなく、大内山の山守ならぬ大内裏の警護役の私は、木の陰から月を観るように、帝のお姿を拝見するのだなあ
この歌によって昇殿を許され、しばらく正四位下であったが、三位に昇進したいと願って、
のぼるべきたよりなき身は木のもとに しゐを拾ひて世をわたるかな=昇進につながる縁故のない私は、木の下で椎の実を拾うように、ここで四位のままずっとお仕えするのだなあ
この歌によって三位に昇進したのだった。すぐに出家して、源三位入道と呼ばれて、今年は七十五歳になられた。
この人が、生涯で一度というほど名をあげたと思われるのは、近衛院がご在位の時、仁平年間に、帝が毎夜毎夜おびえ、魂消ることがあった。祈祷をするとすぐれた霊験を現すという高僧貴僧に命じて、大法秘法を行わせたけれど、その効果はない。帝がお苦しみになるのは午前二時ごろであったが、東三条の森のほうから、黒雲がひとかたまりやって来て、御殿の上を覆うと、必ず帝はおびえなさる。そこで公卿が対策を話し合った。
去る寛治年間のころ、堀河天皇がご在位の時に、同じように帝が毎夜毎夜おびえなさることがあった。そのころの将軍、源義家朝臣は南殿(紫宸殿)の大床に控えていたが、帝がお苦しみになる時刻になると、邪気を払うために、弓の弦を手で引き鳴らすこと三度、その後大声で「前陸奥守源義家」と名のったところ、人々は皆、ぞっとして身の毛がよだち、帝のお苦しみもなくなった。
それゆえ先例に従って、武士に命じて警固させるのがよいと言って、源平両家の武士たちの中から探して、頼政を選び出したということだ。その時はまだ兵庫頭といっていた。
頼政が言うには、「昔から朝廷に武士を置いているのは、反逆する者をとり除き、勅命に背く者を滅ぼすためです。目に見えない変化の物を仕留めよとお命じになることなど、まだ聞いたことがございません」と言いながらも、帝がお決めになったことなので、お召しに応じて参内する。頼政は、厚く信頼する家来の、遠江国住人、井早太に、翼の下のほろ羽のうち、風切り羽をはいだ矢を背負わせて、ただ一人連れてきた。自分は、表裏同色の狩衣に、山鳥の尾ではいだとがり矢を二本、滋籐の弓に添えて持ち、南殿の大床に控えた。頼政が矢を二本たずさえている理由は、雅頼卿が、そのときはまだ左少弁でいらっしゃったが、「変化の物を仕留めるのは、頼政でしょう」と推薦したので、一の矢で変化の物を仕留め損なったら、二の矢で雅頼の弁の奴めの頸の骨を射ようと考えたからである。
ここ数日、人が言っているとおり、帝がお苦しみになる時刻になると、東三条の森のほうから、黒雲がひとかたまり近づいてきて、御殿の上にたなびいていた。頼政がキッと見上げたところ、雲の中にあやしい物の姿がある。もしこれを射損ねたら、生きていられるとは思えない。しかしながら、矢をとって弓につがえ、「南無八幡大菩薩」と心の中で祈念して、矢をひきしぼりヒューッと射る。手応えがあってはたと命中する。「仕留めたぞ、おう」と声をあげたのだった。井早太がすっと近寄り、落ちてくるところを取り押さえて、続けざまに九回切り裂いた。その時、身分の高い者も低い者も、手に手に松明を持って、これを見ると、頭は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎の姿である。鳴く声は鵼に似ていた。恐ろしいという言葉などではとても言い表せない。帝はとても感激なさって、獅子王という剣をお授けになった。宇治左大臣、藤原頼長殿がこの剣を取り次いで、頼政に与えようとして、御前の階段を中ほどまで下りたところで、頃は四月十日すぎのことだったので、郭公が二声三声鳴いて空を飛んでいった。その時、左大臣殿が、
ほととぎす名をも雲井にあぐるかな=ほととぎすが鳴きながら空を飛んでいくように、あなたの評判も宮中(雲居)で高まりましたね
と詠みかけたので、頼政は右の膝をつき、左の袖を広げ、月を少し横目で見ながら、
弓はり月のいるにまかせて=弓張り月が自然に山陰に沈む〈入る〉ように、ただ弓矢にまかせて射るだけでした
と詠み、剣を頂戴して退出した。「弓矢の腕前では肩を並べる者がいないというだけではなく、歌道にも優れていたのだな」と帝も臣下も感動なさった。そしてあの変化の物は丸木舟に入れて流したということだ。
去る応保年間、二条院がご在位の時に、鵼という化鳥が内裏で鳴いて、しばしば帝の眠りを妨げることがあった。先例に従って、頼政をお召しになった。頃は五月二十日すぎの、まだ夜に入ってすぐの時間だったが、鵼はたった一声鳴いて、二声とは鳴かなかった。目を刺しても分からないような闇ではあり、姿かたちが見えないので、的を定められなかった。頼政は思案して、先ず大きな鏑矢を取って弓につがえ、鵼の声がした内裏の上の方に向けて射た。鵼は鏑矢の音に驚いて、空中でしばらくヒヒッと声をあげた。二本目は小さい鏑矢を取って弓につがえ、ヒューッと射て、鵼と鏑矢を同時にみんなの前に落とした。内裏はざわめき、帝のご感動は並々ではなかった。帝がお召しになっていた着物をお授けになると、その時は大炊御門右大臣公能公がこれを取り次いで、頼政に与えようとして、「昔の養由は、雲の上にいる鴈を射た。今の頼政は、雨の中に鵼を射た」と感動を伝えた。
五月闇名をあらはせるこよひかな=梅雨の夜の暗闇の中で、あなたの名を世に知らしめた今宵ですね
と詠みかけたので、頼政は、
たそかれ時も過ぎぬと思ふに=誰なのか、名もわからない夕暮れ時も過ぎてしまったと思いますのに
と詠み、御衣を肩にかけて退出する。
その後、伊豆国をいただき、息子の仲綱を国司にして、自らは三位となって、丹波の五ヶ庄、若狭の東宮河を治めて、そのまま暮らしていけばなんの苦労もなかった人が、つまらない謀反を起こして、それによって高倉宮(以仁王)も命を落とされ、自分の身も滅ぼしてしまったのは、おろかなことであった。
(原文と現代語訳の対訳 ダウンロードはこちらから↓)
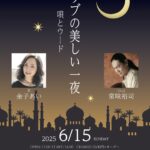

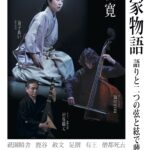
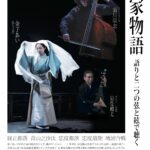
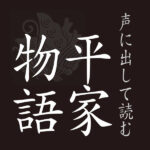




[…] 鵼 現代語訳はこちら […]